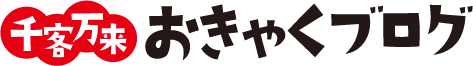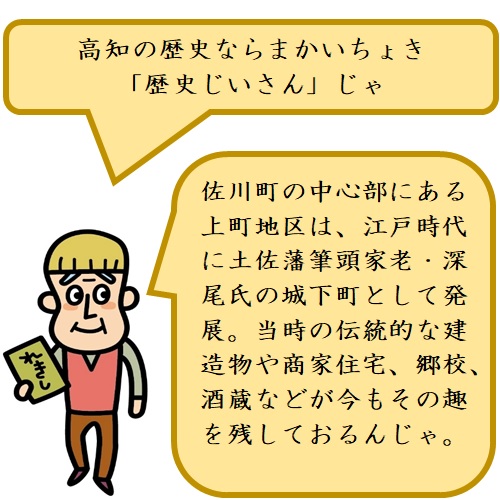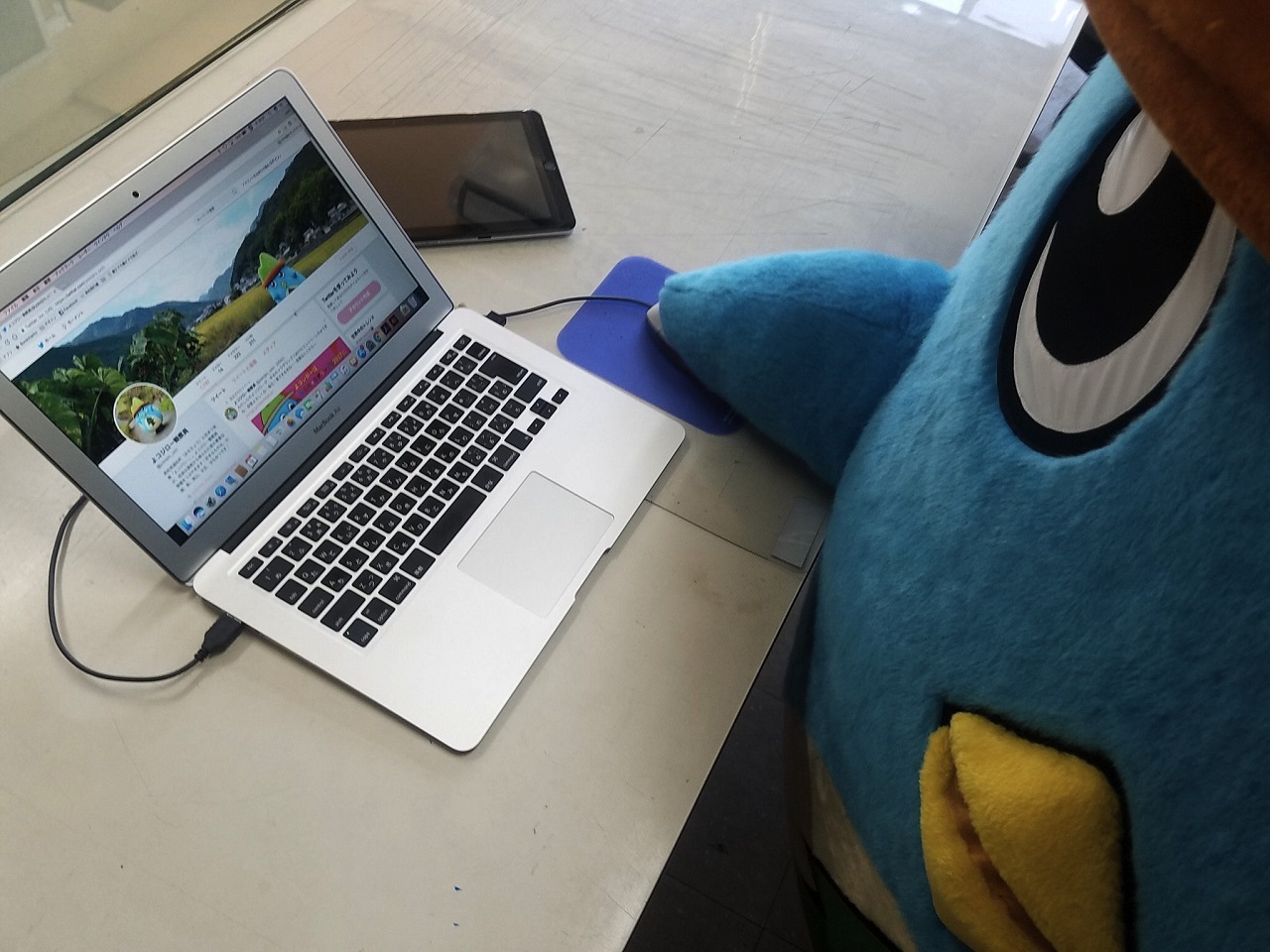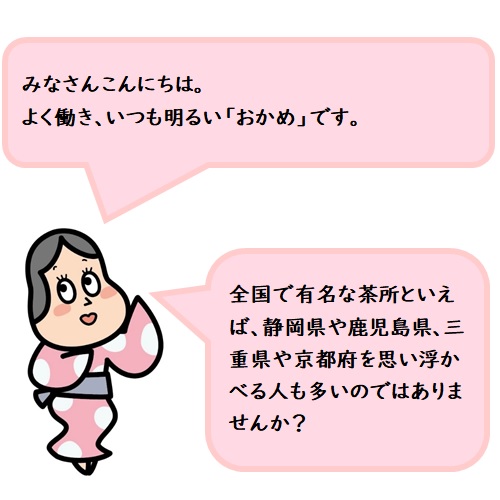いにしえの風情が残る佐川町の町並みと桜
最終更新日:2024年8月19日
#牧野富太郎 #牧野公園 #牧野公園さくらまつり
歴史を感じさせる町並みと同様に、上町地区で知られているのが桜。佐川町出身の植物分類学者・牧野富太郎博士ゆかりの「牧野公園」は日本のさくら名所100選に選ばれており、毎年開花の季節には風情ある町並みと「牧野公園」の桜を見に訪れる観光客で賑わいます。
上町地区でまず訪れていただきたいのは、江戸時代中期に建てられた酒造商家を改修した古民家カフェ「旧浜口家住宅」です。店内では佐川町産の紅茶やケーキを楽しめるほか、町内のお土産の購入も可能。隣接されている「うえまち駅(さかわ観光協会)」では、まちの見所やオススメスポットなどを教えてもらうこともできます。
「旧浜口家住宅」のすぐ近くには、江戸時代より造り酒屋として栄えた商家で、現在は国の重要文化財にも指定されている「竹村家住宅」や、慶長8年(1603)創業の「司牡丹酒造」などがあります。併設のお酒のショールーム「ギャラリーほてい」では、銘酒「司牡丹」などをお求めいただくこともできますよ。
他にも、深尾氏が家塾として創設し、多くの維新志士や偉人を輩出した「名教館」や、鹿鳴館時代の面影を残した、県下最古の木造洋館「佐川文庫庫舎(旧青山文庫)」、牧野富太郎博士の生家跡地に建つ資料館「牧野富太郎ふるさと館」などがあります。
深尾家の菩提寺として慶長8年(1603)に創建された「青源寺」では、土佐三名園の1つといわれている美しい庭園が見られます。現在、上町地区の町歩きガイド(要予約)及び、音声ガイドを実施中。
「旧浜口家住宅」から少し南へ向かうと、日本のさくら名所100選に選ばれた「牧野公園 」があります。ここは、牧野富太郎博士から送られた桜・ソメイヨシノの苗を、地元の有志が「青源寺」の土手などに植えたことから始まり、現在では約350本の桜が公園内に咲き誇る、高知屈指の花見どころです。桜以外にも、博士ゆかりの四季折々の山野草がみられるそうですよ。
「牧野公園」では、令和6年3月22日(金)〜4月7日(日)まで「牧野公園さくらまつり」を開催。桜餅をはじめ、うどんや焼き鳥などの売店、「旧浜口家住宅」での春の生花展や、「司牡丹」の酒粕詰め放題など、様々なイベントが行われます。詳しい日程やイベント内容は、「さかわ観光協会」HPをチェックしてみて下さいね。
今年の春は、佐川町の町並みと美しい桜を楽しんでみてはいかがでしょうか?
取材協力/さかわ観光協会 高知県高岡郡佐川町甲1474
TEL0889-20-9500 https://sakawa-kankou.jp/
~その他「植物学者・牧野富太郎博士」に関する記事~
若かりし頃の牧野富太郎博士ってなかなかの…!?
>>日本の植物分類学を築いた植物学者・牧野富太郎博士
牧野富太郎博士ゆかりの『高知県立牧野植物園』イベント
>>『夜の植物園』へ出かけよう!
知ってますか?牧野富太郎博士にちなんだお酒
>>朝ドラのモデル・牧野富太郎博士にちなんだ香り豊かなお酒♪
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化って知っちゅう?
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
パプリカとポンカンの元気応援ジュース(COLD)
2018.3.15
テーマ:こじゃんとうまい
材料2人分
・黄パプリカ 15g
・ポンカン 100g(1個)
・小玉トマト 75g
・飲むヨーグルト 150ml
・ハチミツ 30g(大さじ2前後・適宜増減)
・氷
「作り方」
1.黄パプリカは1cm角に切る。ポンカンは皮をむいて4つに分ける。トマトはへたを取る。
2.材料をミキサーにかける。
ポンカンの房と黄パプリカが残らないようにミキサーは長めにかけた方が良い。
○ レシピ提供 高知県園芸連
越知町商店街に誕生した「SHOPおちぞね」
2018.3.9
テーマ:土佐のイチオシ
よさこいおきゃく支店の渉外担当「いごっそう」です。
今回は、高知県の中央部に位置する越知町に新拠点「SHOPおちぞね」が誕生したとの噂を聞きつけ、さっそく調査に伺いました!
20年程前から空き家となっていた商店街の建物が、“クリエイティブなモノ・コトづくりができる交流の場”をコンセプトにした、地域活性化拠点兼チャレンジショップとして生まれ変わりました。店名の「おちぞね」とは土佐弁で「越知だよ」という意味で越知のことを身近に感じてほしいという思いが込められているそうです。
チャレンジショップとは、将来開業を目指している方が、本格的な開業の前にお試し出店ができる施設のこと。木造2階建ての「SHOPおちぞね」の1階はサービス業や物品販売などの出店ができるチャレンジショップと、交流や休憩所として立ち寄れるコミュニティスペースになっています。そして、2階に2間ある和室はワークショップや習い事、イベントなど、多目的に利用できます。
また、建物内には越知町の地域おこし協力隊の事務所も併設されていて、隊員たちがショップの運営に協力してくれるそうです。地域おこし協力隊は、越知町のCM作成や仁淀川山椒を使った焼肉のたれなどの特産品開発、越知町の魅力などを掲載している無料冊子「おちぞね」も発行し、地元の新聞でも活躍が取り上げられているすご腕揃い!東京でデザイナー経験をもつ隊員もいて、チャレンジショップ出店中はポップの制作やネット通販なども一緒に考えてくれるそうです!!
越知町内で、起業を目指したい、趣味や特技を活かしたワークショップなどを開催したい、という方は越知町企画課に問い合わせてみて下さいね。
今後どんなお店が出店するかワクワク♪今後も「SHOPおちぞね」から目が離せませんよ!
●SHOPおちぞね 高知県高岡郡越知町越知甲2484-3
問合せTEL0889-26-1164(越知町企画課)
※本記事の内容は、2018年3月9日時点の情報となります。
仁淀ブルーに染まった横倉山の妖精「よコジロー」
2018.3.2
テーマ:土佐のイチオシ
最終更新日:2025年1月28日
みなさんは、高知県越知町の横倉山をご存知ですか?誰でも気軽に登山や散策を楽しめる山でありながら、太古の地層や安徳天皇が隠れ住んだといわれる平家伝説を持つ、神秘のベールに包まれた山なんですよ。
実は、この山には「よコジロー」という妖精が住んでいるんです!
 「よコジロー」は、仁淀ブルーに染まった体と、横倉山の形をした帽子、町内の大きな杉の木に激突した時にくっついたお腹の杉が特徴的な、メジロの姿をした越知町のイメージキャラクター。口にくわえた一輪のコスモスは、奥さんに贈るためにコスモスまつりで有名な宮の前公園で摘んだんだとか。ユニークで愛らしい姿が人気となり、昨年開催された「ゆるキャラグランプリ2017」では、高知県(ご当地キャラ部門)で1位に輝きました!
「よコジロー」は、仁淀ブルーに染まった体と、横倉山の形をした帽子、町内の大きな杉の木に激突した時にくっついたお腹の杉が特徴的な、メジロの姿をした越知町のイメージキャラクター。口にくわえた一輪のコスモスは、奥さんに贈るためにコスモスまつりで有名な宮の前公園で摘んだんだとか。ユニークで愛らしい姿が人気となり、昨年開催された「ゆるキャラグランプリ2017」では、高知県(ご当地キャラ部門)で1位に輝きました!
「よコジロー」の趣味は川遊びや森林浴、好物は町内にある松田精肉店のコロッケ。
親友は「高知ファイティングドッグス」のマスコット「ドッキー」だそうです。鳴き声は「おちつくなぁ」というユニークな「よコジロー」は、現在子育てに奮闘中!?でも家族の姿を見かけた人はあまりおらず、その姿を見た人は幸せになれるという言い伝えがあるんだとか。
「観光物産館おち駅」では、「よコジロー」のぬいぐるみやストラップ、お菓子などのグッズを販売しています。
おち駅の交流スペースと「横倉山自然の森博物館」内には、「よコジロー」のガチャガチャも設置されていますよ。
「よコジロー」は、2018年の10月27・28日に開催される「第38回全国豊かな海づくり大会~高知家大会~」のPRキャラクターにも選ばれています。HPやツイッターで活動を公開してるのでチェックしてみて下さいね♪
越知町HP→ http://www.town.ochi.kochi.jp/
よコジローツイッター→ https://twitter.com/yokojiro_ochi
↓高知県のゆるキャラ紹介します!↓
■高知と言ったら…カツオ…人間?
■高知県須崎市発の全国区ゆるキャラ
■高知県香南市の水先案内人と言えば…
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化って知っちゅう?
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
土佐の茶所・仁淀川町の良質なお茶と茶農家手作りスイーツ♪
2018.2.23
テーマ:ろいろいしゆう記
最終更新日:2025年1月28日
実は、高知県は良質なお茶の産地。「土佐茶」は、静岡県をはじめとするお茶の名産地から荒茶(一次加工したお茶)として買付されるほど人気が高いんです!!
今日は、仁淀川町で栽培されている風味豊かな「土佐茶」をご紹介します。
仁淀川町は、仁淀川の綺麗な水と冷涼な空気や朝露、山間部ならではの寒暖差により良質な茶葉が育つ、高知県を代表する茶栽培の適地です。江戸時代には、お殿様にお茶を献上するほどの、高品質なお茶が栽培されてきました。地域の茶農家8名が、減農薬の“旨い茶”の生産をめざして平成5年(1993)に「池川茶業組合」を設立し、設立後に出品したお茶は、高知県茶品評会の高知県知事賞や、関西茶品評会では農林水産大臣賞など、数々の賞を受賞している逸品です!
茶農家が大切に育てたお茶を味わっていただこうと、2011年には茶農家の女性5名が、茶スイーツの工房兼カフェ「池川茶園」をオープンしました。仁淀川の支流・土居川を眺めながら、厳選した茶葉を使用したスイーツが味わえるとあって、連日多くの人が訪れているそうですよ。
手作りのスイーツはどれも人気商品ばかり。「かぶせ茶」と「ほうじ茶」の2種類の味が楽しめる「茶畑プリン」と池川一番茶と高知県産の生クリームをたっぷり使ったほろ苦い大人の味の「茶畑ロール」は必食!!他にも、茶葉をベースにしたソフトクリーム、煎茶パウダーをふんだんに使った生チョコレート、みずもちや茶畑ラスクなどをトッピングした「茶畑パフェ」も外せません♪
スイーツは、「池川茶園」のHPからも購入できます。「土佐茶」をしっかり感じられる茶農家ならではの手作りスイーツと、仁淀川町で大切に育てられた良質なお茶を、ぜひご堪能ください。
●池川茶園 工房Cafe 高知県吾川郡仁淀川町土居甲695-4
TEL0889-34-3100 https://www.ikegawachaen.jp/
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化をご紹介!
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
忍者気分で洞窟探検!自然のままの地形が残る「猿田洞」
2018.2.16
テーマ:ろいろいしゆう記
最終更新日:2025年1月28日
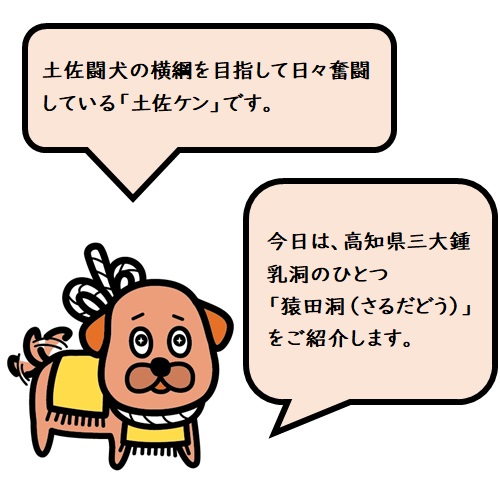
「猿田洞」は本洞、支洞を合わせると全長約1420mの3層に分かれている石灰洞で、現在はそのうちの200mほどが探検用に開放されています。
 この洞窟は、付近に住んでいた農民・虎之丞によって安政5年(1858)に発見されました。江戸時代中期頃に活躍した義賊的な忍者・日下茂平(くさかもへい)が修行をしたという伝説もあり、開口当時は1日に数百人の見物人が訪れ、入口付近には売店が軒を並べるほど人気があったそうです。昭和35年(1960)には日高村の文化財に指定され、一般の方も探検できるように整備されました。洞内では、2万年前に棲息していた赤鹿の骨なども発見されたそうですよ!!
この洞窟は、付近に住んでいた農民・虎之丞によって安政5年(1858)に発見されました。江戸時代中期頃に活躍した義賊的な忍者・日下茂平(くさかもへい)が修行をしたという伝説もあり、開口当時は1日に数百人の見物人が訪れ、入口付近には売店が軒を並べるほど人気があったそうです。昭和35年(1960)には日高村の文化財に指定され、一般の方も探検できるように整備されました。洞内では、2万年前に棲息していた赤鹿の骨なども発見されたそうですよ!!
手つかずの自然を残した洞内は真っ暗でスリル満点!はしごやロープなどの少ない設備だけを頼りに、人ひとりがなんとか通れるような狭い場所や深淵、垂直の壁などを、五感をフル活用して進んでいく・・・まさに修行をしている気分を味わえます!!懐中電灯や軍手、ヘルメットは必須。滑りにくい靴や長袖・長ズボンを着用してチャレンジしてくださいね。探検初心者や子どもがいる場合は、装備のレンタルや洞内ガイドがつくケイビングツアーへの参加がおすすめです♪
「猿田洞」は、ひとりでの入洞は禁止なので、必ず2名以上で入洞してください。入洞前には必ず日高村教育委員会に連絡し、入洞許可を得て、自然のままの洞窟を探検してくださいね♪
●猿田洞 高知県高岡郡日高村沖名1619
お問い合わせ TEL0889-24-5115(日高村教育委員会)
https://www.vill.hidaka.kochi.jp/kankou/spot_23_watch.html
猿田洞ケイビング お問い合わせ
TEL:050-3204-1996(日高村観光協会)
FAX:0889-24-5888
https://www.hidakamura.info/sarudacaving
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化をご紹介!
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
四国4億年の歴史や珍しい化石に出会える「佐川地質館」
2018.2.9
テーマ:ろいろいしゆう記
最終更新日:2025年1月28日
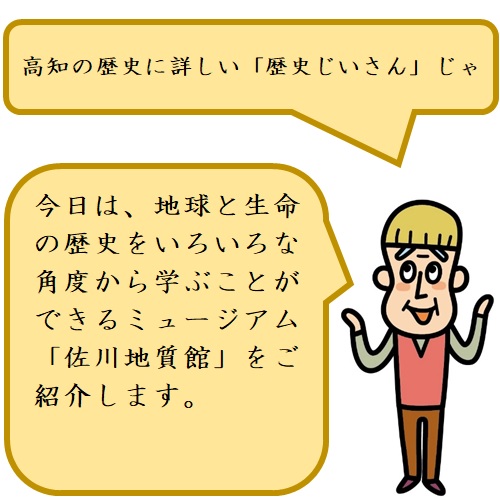
佐川町は高知県の中西部に位置する盆地状の町で、古生代から中生代の「化石の宝庫」として知られています。日本列島の生い立ちを探る上できわめて重要な地域として、ドイツ人の地質学者ナウマン博士や、小林貞一博士らによって古くから研究が行われてきました。
「佐川地質館」は佐川町で発見された化石をはじめ、高知県内の地形・地質に関する資料などを収集・保管・展示し、郷土の文化及び学術の振興に寄与することを目的として、平成4年(1992)に開館しました。
館内のエントランスホールでは巨大なティラノサウルスがお出迎えしてくれます。リアルな動きと大きな鳴き声が子どもたちに大人気。あまりの迫力に泣いてしまう子どももいるんですって!!
メインの主展示室では、約2億5000万年前に存在したといわれる超大陸・パンゲアが分裂・移動する様子を見られる大陸装置や、高知県の地図に沿った地形や地質、化石を紹介・展示していますよ。


他にもナウマン博士や小林博士に関する資料、世界最古の化石、人気の三葉虫やアンモナイトの化石を展示している研究史コーナー、日本列島の成り立ちや佐川盆地の地質の特徴などを紹介するジオファンタジック・ルーム、恐竜の化石を発掘する様子などを3Dで上映する立体映像室などなど・・・楽しみながら学べるコーナーが盛り沢山!屋外展示場では約1億3000万年~7500万年前の地層や岩石を観察したり「鳥ノ巣石灰岩山地質トンネル」の探索もできちゃうんですって♪
夏休みにはアンモナイト化石のクリーニング教室、秋には化石採集の体験教室などもあるそうです。詳しくは、「佐川地質館」のHPをチェックしてみてくださいね。
みなさんも、佐川町の地質や化石に触れて、太古のロマンを肌で感じてみませんか?
●佐川町立 佐川地質館 高知県高岡郡佐川町甲360
TEL0889-22-5500 https://sakawa-geomuseum.jp/
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化って知っちゅう?
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
「によどの日」ロビー展
2018.2.7
テーマ:イベント
みんなぁおはよう!
「仁淀ブルー」で有名な仁淀川が流れよる高知県には「によどの日」ってゆうのがあるがやけんど、いつか知っちゅう?
なんでも、『「24日の土曜日」を語呂あわせで「によどの日」にしよう!』と云うた人が居ったらしゅうて、二年ばぁ前からじわ~っと拡がってきゆうがよ。
今年は2月と3月の土曜日が、ぼっちり「によどの日」になるきに「こりゃあ、へんしも何かせんといかん」ちゅうことで、仁淀川流域にある「こうぎん」の6つの支店でロビー展をすることにしたがぁ!!
銀行のロビーに、仁淀ブルーの綺麗な写真や観光情報らぁを並べて、支店それぞれのご当地展示物もかまえちゅう。簡単なアンケートに答えてもろうたら、その場で仁淀ブルーグッズが当たるスピードくじもやりゆうで。
展示期間は平成30年2月13日(火)~3月26日(月)で、
2/13~16 佐川支店 ⇒ 2/19~23 池川支店 ⇒ 2/26~3/2 越知支店 ⇒ 3/5~9 伊野支店 ⇒ 3/12~16 宇佐支店 ⇒ 最終 3/19~26 高岡支店
の順番で仁淀川を上ったり下ったりするけんど、かまんかったら見にきてつかぁさい。窓口の行員が仁淀ブルーの法被でお出迎えさぃてもらいます。
待ちゆうきね!!
[投稿者 高岡支店 仁淀ブルーマン]
200年以上伝わる、土佐三大祭りのひとつ「秋葉まつり」
2018.2.2
テーマ:ろいろいしゆう記
最終更新日:2025年1月28日
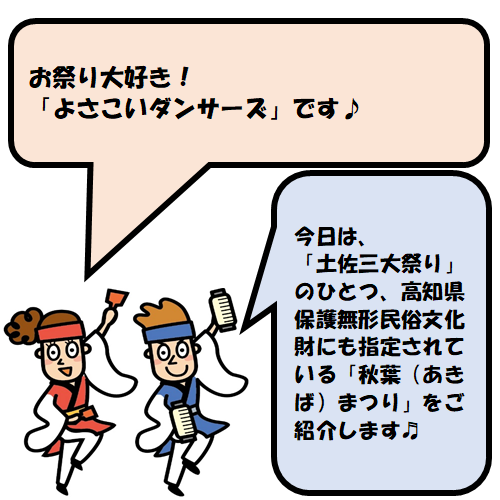
高知県には「よさこい祭り」をはじめ、歴史ファンが集う「長宗我部まつり」、飲兵衛が参加する「どろめまつり」など、地元の人も観光客も楽しめるお祭りがたくさん開催されています。
今日は、そのなかでも「土佐三大祭り」のひとつ、高知県保護無形民俗文化財にも指定されている仁淀川町の「秋葉(あきば)まつり」をご紹介します。
「秋葉まつり」は愛媛県との県境に位置する仁淀川町からさらに奥、別枝地区にある秋葉神社の祭礼で、毎年2月9日〜11日に行われています。
その起源は古く、平家一門に随行していた佐藤清岩(さとうせいがん)が、遠州(現在の静岡県)にある秋葉神社の御祭神を分霊し、仁淀川町の岩屋神社裏に祀ったのが始まりといわれています。御祭神はその後、国境の関所番を務めていた市川家に祀られ、寛政六年(1794)に地区全体の氏神様として秋葉神社に移されました。
その際、年に一度、ゆかりの地に御神幸する約束となったことから、御神体は初日(2月9日)に岩屋神社、2日目(10日)に市川家にお渡りし、最終日(11日)に秋葉神社に戻られるようになったそうです。
祭りの最終日(11日)には本村、霧之窪、沢渡の3集落から集まった役者、総勢約200人が岩屋神社から秋葉神社までの約3kmの細い山径をゆっくりと練り歩きます。先払いの鼻高面を先頭に、お囃子を演奏しながらゆかりの地を巡るこの行列は、地元では「練り」と呼ばれ素朴でありながらもそこはかとなく雅な風情を醸し出しています。
「秋葉祭り」の山場は長さ7mのヒノキの棒の先端に鳥の羽を付けた鳥毛(とりげ)を、約10m離れた2人が投げあう鳥毛ひねり!重さ8kgにもなる鳥毛が宙を舞い、見事キャッチされる瞬間には、見物客から大きな歓声があがります。その他、太刀踊り、お神楽など見どころ満載です。「練り」の道中では、ユーモラスな仕草が笑いを誘う、お面をつけた油売りが、房のついた小さい「サイハラ」と呼ばれる火防のお守りを売りに現われるんですって。ぜひ見つけてみてくださいね。
「秋葉まつり」では、仁淀川町特産のヨモギが入った名物「いりもち」や軽食、屋台もあります。神幸行列と一緒に山径をゆっくり歩いた後は、この地区ならではの美味しい料理で身体を温めてくださいね。お祭りの詳しいスケジュールは仁淀川町役場のHPからチェックできますよ。
●開催場所/岩屋神社〜秋葉神社(高知県吾川郡仁淀川町別枝本村)
問合せTEL0889-35-1083(仁淀川町役場 産業建設課) https://www.town.niyodogawa.lg.jp/kanko/
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化って知っちゅう?
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
最近の投稿
テーマ
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |