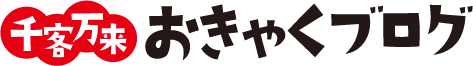2017年7月14日
18節もの舞で構成された重要無形民俗文化財「津野山神楽」
2017.7.14
テーマ:ろいろいしゆう記

今日は、県外からも多くの人が訪れる、高知県梼原町の伝統的な舞楽「津野山神楽」をご紹介します。
「津野山神楽」は、その年の五穀豊穣に感謝する秋祭りとして毎年10月下旬〜11月にかけて行われ、「三嶋神社/川西路」(10月30日)「三嶋五社神社/田野々」(11月3日)「三嶋神社/竹の薮」(11月23日)など各集落の神社に奉納されます。
「津野山神楽」がいつの頃からどのようにして、この地に興ったものか定かではありませんが、延喜13年(913)藤原経高(ふじわらのつねたか)が津野山郷(梼原町・津野町一帯の山村地帯)へ入国し、 伊予の国(愛媛県)より「三嶋神社」を歓請して祀った頃より代々の神官によって歌い継ぎ、舞い継がれたものとされています。昭和23年(1948)には、当時の町長を中心に「津野山神楽保存会」を結成。昭和55年(1980)には、土佐の神楽の一つとして国の重要無形民俗文化財に指定されました。
全部で18節からなる「津野山神楽」の舞いは、進む時・退く時・座る時・立つ時に、「進左退右」「座左起右」という作法が決められており、 正式に舞い納めるには、なんと約8時間を要するそうです。軽快な囃子に合わせたダイナミックな動きでありながら、優美さを決して失わない雅な舞が、見る者を魅了します。

 「津野山神楽」は、「第一節・宮入り」からはじまり、無事に神楽が終わりましたと願いごとを解くための「第十八節・四天」で舞納めとなります。演目の中には、天照大御神(あまてらすおおみかみ)や天狗のような鼻長の猿田彦(さるだひこ)、七福神のひとりであるえべっさまなどが登場し、ひとつひとつの舞に様々な物語を見ることができます。中でも人気の「第六節・大蛮」は、暴れん坊の神・大蛮(だいばん)が7つの宝を神様に返上するという物語なのですが、返上する際に宝の特徴をひとつずつ説明するセリフがとてもユーモラスなんです。また、生後1年未満の赤ちゃんを抱いて舞う場面もあり、無病息災を願う子ども連れの家族も多いんですよ。
「津野山神楽」は、「第一節・宮入り」からはじまり、無事に神楽が終わりましたと願いごとを解くための「第十八節・四天」で舞納めとなります。演目の中には、天照大御神(あまてらすおおみかみ)や天狗のような鼻長の猿田彦(さるだひこ)、七福神のひとりであるえべっさまなどが登場し、ひとつひとつの舞に様々な物語を見ることができます。中でも人気の「第六節・大蛮」は、暴れん坊の神・大蛮(だいばん)が7つの宝を神様に返上するという物語なのですが、返上する際に宝の特徴をひとつずつ説明するセリフがとてもユーモラスなんです。また、生後1年未満の赤ちゃんを抱いて舞う場面もあり、無病息災を願う子ども連れの家族も多いんですよ。
みなさんも、一千年以上の歴史を持つ梼原町の「津野山神楽」をぜひ見に行ってみてくださいね。
「三嶋神社/川西路」…役場より徒歩5分
「三嶋五社神社/田野々」…役場より車で10分
「三嶋神社/竹の薮」…役場より車で10分
●取材協力/梼原町教育委員会
問合せTEL0889-65-1350 http://www.town.yusuhara.kochi.jp
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
高知をこじゃんと応援中!
![]()
よさこいおきゃく支店とは?
申し込み方法がよりスマートになりました!
→口座開設申込みの流れ
高知のおきゃく文化をご紹介!
☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★
最近の投稿
テーマ